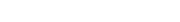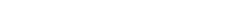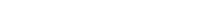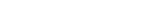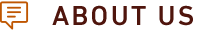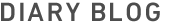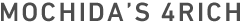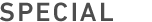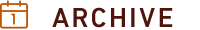浅草「酉の市」でドヤれる豆知識

GREのkawanoです。
個人的に毎年ぶらっと立ち寄る
11月の風物詩、浅草の「酉の市」。
縁起物の「熊手(くまで)」を求める人々で溢れかえる、あの熱気は圧巻です。
でも、ただ「熊手すごい!」だけじゃもったいない。知っていると10倍楽しめる、酉の市の「うんちく」を端的にご紹介します。

1. なぜ「熊手」なの?
酉の市=熊手ですが、なぜ熊手なのでしょうか。 それは、「福や金運を”かき集める”」 という、非常にわかりやすいゲン担ぎのため。あの手の形で、幸運をガッチリ集めるわけです。
【小うんちく】 熊手は、前年よりも少しだけ大きいものを買うのが「粋」とされています。毎年商売が少しずつ大きくなっていく、という縁起を担いでいます。
2. 浅草の酉の市は「2ヶ所」で開催されている
「浅草の酉の市」と一口に言いますが、実は会場は2つあります。 それが、「鷲神社(おおとりじんじゃ)」と、お隣の「長國寺(ちょうこくじ)」。
これは、昔の「神仏習合(神様も仏様も一緒に祀る)」時代の名残です。明治時代に分けられましたが、今でも両方でお参りするのが通とされています。
3. あの「手拍子」は何?
市を歩いていると、あちこちから「イヨーッ!」という掛け声と共に、リズミカルな手拍子が聞こえてきますよね。 あれは「手締め(てじめ)」です。
大きな熊手が売れると、お店の人とお客さんが一緒になって、来年の商売繁盛を祈願して行う儀式。あの威勢の良い手拍子こそ、酉の市の活気の源です。
4. 「三の酉」がある年は…
11月中に「酉の日」が3回ある年を「三の酉(さんのとり)」と呼びます。 古くから「三の酉がある年は、火事が多い」という言い伝え(迷信)があります。江戸っ子たちは「火の用心!」と、より一層気を引き締めたとか。
うんちくを知ってからあの活気の中に飛び込むと、聞こえてくる手締めや、隣り合う神社とお寺の不思議な光景も、また違って見えてくるはずです。
是非浅草へ!